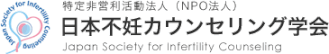お灸教室
お灸教室 · 2025/02/01
2月は花粉の飛散が活発になったり、天候や気温が激しく変動したりするため、体調を崩しがちです。 「春浅し」「春めく」 雪の季節から桜まで大きく変化する春には、刻々と移りゆく気候の変化を語る言葉がたくさんあります。 「春の淡雪」は、手のひらで受けると瞬間に消えるはかない雪、日差しも少しずつ柔らかくなっていきます。...
お灸教室 · 2024/12/01
新年を迎えるために、大掃除や様々な準備をする月となりました。 この時期になると、あまりに早い月日の流れに、つい慌ててしまいます。 だからこそ、お灸でちょっと一息ついてみましょう。
お灸教室 · 2024/11/02
11月に入り、朝晩との温度差が激しく、思った以上に身体や自律神経に負担がかかっています。 このような、温度変化が大きいときは、肉体面だけではなく、精神面にも影響を及ぼします。 肉体的な不調として、頭痛やめまい、肩こりなどの症状があらわれます。 精神的な不調として、自律神経の乱れにより、イライラや不安、落ち込みなどの症状があらわれます。...
お灸教室 · 2024/09/30
暑かった夏も終わり、ようやく秋めいてきました。 この時期は、気候の変化とともに体調の変化も起こりやすくなっております。 こんな時に「お灸」を試してみませんか? あなたの症状に合ったツボを見つけて、 あなただけの“Myツボ”を探していきましょう。
お灸教室 · 2024/09/02
9月に入り、早朝、草の葉に白く光る露が目立ってきます。 白は秋を表す言葉です。 今月の7日は二十四節気の「白露」で、まさに秋を表しています。 秋を迎えると、咳が出る人や、足のふくらはぎがつる人が増えてきます。...
お灸教室 · 2024/07/30
7月24日につづき、8月5日は、夏の土用の丑の日です。 夏の土用は、立秋の前の18日間をいい、高温多湿の夏をスムーズに乗り切るために、栄養価の高いウナギを食べる習慣が生まれました。 ちなみに、大暑(一年で最も暑い時期。今年は7月22日)から立秋(本格的な酷暑の時期。今年は8月7日)にかけては、蒸し暑さがピークです。...
お灸教室 · 2024/07/01
今年の7月24日(水)と8月5日(月)は、夏の土用の丑の日です。 夏の土用は、最も暑さが厳しいとされる時期です。 暑い夏を乗り切るために、一般的には、うなぎを食べたりしますが、お灸を据える「土用灸」という養生法もあります。 梅雨明けとともに、高温多湿の夏が来ます。 土用灸を用いて、暑い夏を乗り切りましょう。
お灸教室 · 2024/06/05
6月は梅雨の季節! 雨の日が続くと、ジメジメ、ベタベタで身体が重くやる気が出ない、こういった方は多いのではないでしょうか。 次のような症状がある方は、“湿邪”の影響を受けている可能性があります(湿邪=東洋医学の病因の一つで、不調の原因と言われています)。 身体がだる重い 手足が重い 頭が重い・痛い むくみがいつもより酷い 胃が使えた感じ
お灸教室 · 2024/04/02
4月は気候や環境が変わり、生活のリズムや自律神経が乱れがちに・・・。 こんな時に、お灸を用いてリラックスしてみませんか。 お灸を用いて身体全体のバランスを整え、自然治癒力を高めて、体質改善を目指しましょう。
営業日カレンダー
3月のお灸教室は、第3日曜日の3月16日(日)に行います。完全予約制のため、3月11日(火)までにご予約ください。
1 (税込)
概要 | 利用規約 | 返金条件と返品取消申請書 | 配送/支払い条件 | プライバシーポリシー | サイトマップ
Copyright © 2012 山本鍼灸院 All Rights Reserved.
Copyright © 2012 山本鍼灸院 All Rights Reserved.